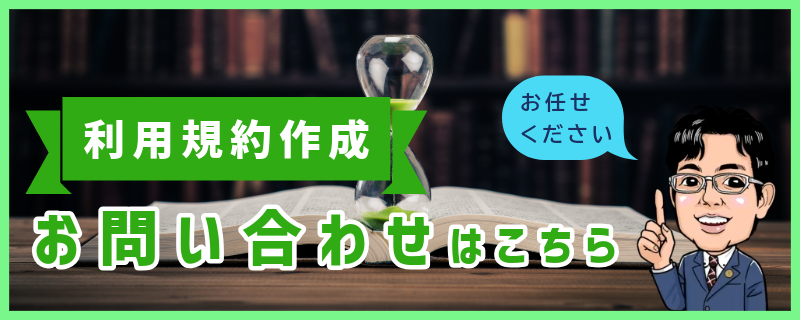利用規約は、サービス提供者と利用者の間でルールを定めるもので、法律上は契約に該当します。しかし、作成してサイトに掲載しただけで「これで安心」と思っていないでしょうか。実は、利用規約は作成するだけでは不十分で、相手方である利用者の同意がなければ、契約としての効力を発揮しないことがある点に注意が必要です。
利用規約はいわゆる「契約」
利用規約は、サービス利用の条件や禁止事項、責任の範囲などを定めている文章ですが、この内容を一方的に押し付けることはできません。
契約は日本の民法で「当事者双方の合意」によって成立するとされており、利用者が同意していない利用規約は、その効力が否定されるリスクがあります。
「表示」と「同意」のセットが不可欠
ここで重要なのは、利用規約を「表示」し、その内容を契約条件とする旨の合意を得ることです。単に「当サービスの利用規約が適用されます」というだけでは、法的には十分とはいえません。
特に、契約が成立する場面(例:会員登録時や購入手続き時)で、利用者がその規約をしっかりと確認できる状態にあることが求められます。
この「表示」とは、単に「規約がありますよ」と知らせるだけではなく、契約締結画面までの間で、利用規約を画面上で明確に認識できる状態に置くことを意味します。
例えば、登録フォームに「利用規約はこちら」といったリンクを目立つ場所に設置し、「同意する」のチェックボックスを設けるなどが基本です。
加えて、いつ・どの利用者が同意したかの履歴を残すことも、トラブル防止に有効です。
なお、「表示」については、2020年の民法改正で新設された民法548条の3(定型約款の内容の表示)も重要です。
同条では、利用者が定型約款の内容を知る権利を保障する必要があることから、契約締結後の相当な期間内であっても、利用者から請求された場合は遅滞なく定型約款(利用規約)の内容を示すことが義務付けられています。
(定型約款の内容の表示)
第五百四十八条の三 定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。
ここで注意が必要なのが、上記条文で太字にした箇所です。
特に、契約締結後であっても利用者から規約の内容の開示を求められた場合には、規約の内容を示さなければならないのですが、例外として、規約を記載した書面をすでに交付していたり、規約内容を記録した電磁的記録(PDFやメールなど)を提供していたときに限り、その表示義務が免除されます。
つまり、ウェブサイト上に規約ページが存在しているだけでは「規約内容を記録した電磁的記録の提供」ではないため、この例外事項には該当せず(経済産業省『電子商取引及び情報財取引等に関する準則(令和7年2月)』p31 より)、請求を受けた際には規約内容を示さなければなりません。
なお、ウェブサイト上の規約ページのURLを案内することも「相当な方法」であるとされています(筒井 健夫・村松 秀樹 編著『一問一答 民法(債権関係)改正』商事法務 p255 脚注1)ので、請求を受けた際はこの方法でも問題ありません。
※ただし、例えば請求者がネットを見ることができないと言っているにも関わらずURLを回答するだけでは、契約内容等によっては表示義務違反となる可能性があります
規約はすぐにアクセスできる場所に設置
先述のとおり、一度同意を得た後であっても、契約内容を知る権利を保障する必要があるため、利用規約は利用者が必要なときにすぐ確認できるようにしておくことが大切です。
目安としては、どのページからも1~2クリックで到達できる場所にリンクを設置するのが望ましく、一般的にはフッターに常設することが多いです。
さらに、規約を改定する際には、利用者にその旨を周知し、改めて同意を取得したり、改定後も引き続き利用する意思があるかを確認する対応が必要です。
(参考)利用規約を勝手に変更してはいけない?令和2年民法改正の影響とは
このようなアクセスのしやすさは、契約の公正性・透明性を担保するものとして、利用者の信頼を高める役割も果たします。
効力が弱くても「抑止力」になることも
では、仮に利用者から十分な同意を得られていなかった場合、利用規約は完全に無意味なのでしょうか。
実際にはそうとも限りません。たとえ裁判などで規約の適用が認められなかったとしても、利用規約がきちんと整備され、公開されていること自体が抑止力として機能することがあります。
例えば、禁止事項が明示されていることで「やってはいけないこと」が明確になるため、利用者としてはその行動を慎む方向に進みやすく、また悪意のある利用者が「このサイトは規約がしっかりしているので問題を起こすと不利になる」と考え、違反行為を控えるケースも想定されます。
適切に同意を得ておくことが望ましいことはもちろんですが、規約を用意しておくこと自体は無駄ではありません。
まとめ
利用規約の作成が済んでいる場合、次に問うべきは「その運用は本当に万全か?」ということです。作っただけで満足してしまうと、いざという時に規約が期待どおり機能しないリスクがあります。
「作成」だけでなく「有効な契約として機能する運用」にも意識を向けることが、法的リスクを減らし、利用者の信頼も高めることにつながります。
作っただけになっている利用規約に思い当たる方は、今からでも見直してみてはいかがでしょうか。