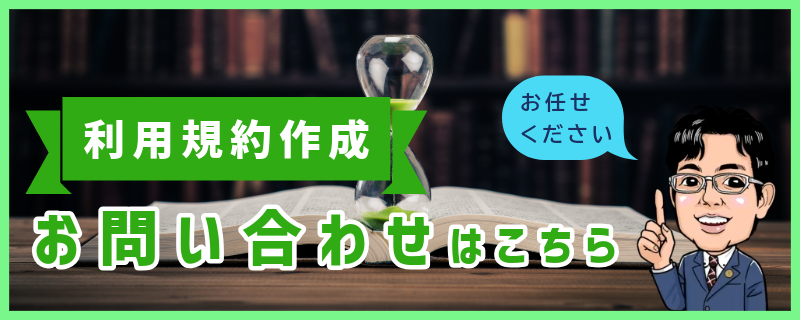インターネットサービスやECサイトの普及に伴い、サービス運営者が「利用規約」を用意するのは当たり前(更に言えば、必須)の時代になりました。
特に、サービス運営者側のリスクを軽減するための「免責条項」は、多くの規約で見かけます。
しかし、免責条項をただ盛り込めばよいというわけではありません。
内容によっては消費者契約法に違反し、無効となったり、サービス運営者が責任を問われたりすることもあります。
本記事では、利用規約の免責条項と消費者契約法の関係、そして実務で注意すべきポイントを解説します。
免責条項とは?
免責条項とは、サービス運営者がサービスの利用者に対して負う責任を限定、または免除するための条項のことをいいます。
例えば、代表的な規定としては以下のようなものがあります。
当社は、ユーザーに対する本規約に基づく措置について一切の責任を負わない。
当社は、提供する情報の正確性・完全性・有用性を一切保証しておりません。
天災地変、通信障害、第三者の不正行為による損害について、当社は一切の責任を負わないものとする。
こうした条項は、サービス運営者側が予期しないトラブルや過度な賠償責任を回避するために設けられています。
なお、免責条項自体は十分価値のあるものであり、例えば利用者からの理不尽な要求(いわゆるカスタマーハラスメントなど)からサービスや担当者を守るといった役割があります。
よくある誤解とリスク
サービス運営者が免責条項を作成する際、先述の例のように「一切の責任を負わない」と書いておけば安心、といった考えがあるような印象を受けます。
しかし、実際には「一切の責任を負わない」という包括的な免責条項は、消費者契約法により無効と判断される可能性が高く、むしろリスクを高める結果になりかねません。
これは小規模な事業者や個人開発者であっても例外ではなく、消費者契約法の対象となる以上、適切な免責条項の設計が求められるのです。
消費者契約法と免責条項の関係
では、消費者契約法とはどのような法律なのでしょうか。
消費者契約法は、サービス運営者などの事業者と、利用者である消費者との契約(BtoC)において、その契約が無効になったり取り消すことができる場合というのを定めています。
それにより、免責条項に関しては「消費者の利益を不当に害する契約条項」、つまり「当社はすべての責任を負わない」といった条項は、無効とされる可能性が高いのです。
なお、「無効」とは、その規定による効力が最初から無かったものになることをいいます。
裁判になった例も
実例として有名なのが、株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA)の運営する「モバゲー」の利用規約をめぐる裁判です。
この事件では、適格消費者団体「特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会」が、消費者契約法に違反する条項の使用差止めを求めて、2018年7月9日にさいたま地方裁判所に提訴したものです。
問題となったのは、主に「当社は一切の責任を負いません」といった条項でしたが、裁判所(第一審のさいたま地裁、控訴審の東京高裁のいずれも)はこれらが消費者契約法で無効として定めるものに該当すると判断しました。
※詳しくは「埼玉消費者被害をなくす会と株式会社ディー・エヌ・エーとの間の訴訟に関する控訴審判決の確定について」(消費者庁)参照
この事件は、個別の消費者トラブルではなく、将来の被害を防ぐための「差止請求訴訟」として行われた点でも重要な事例です。
無効となる条項例
次のような条項は無効と判断されるリスクが高いため、もし公開中の利用規約に同様の規定がある場合は、早急に見直すことが必要です。
いかなる理由があっても一切損害賠償責任を負わない
当社は、商品の品質等に不適合があっても、一切損害賠償、交換、修理をいたしません。
消費者が事業者に故意又は過失があることを証明した場合には損害賠償責任を負う。
法律上許される限り、○万円を限度として損害賠償責任を負います。
※消費者庁「消費者契約法 逐条解説 第2節」を元に作成
無効を避けるための利用規約作成のポイント
このように、規定内容によっては規約が無効と判断される場合があるため、利用規約において免責条項を定める場合は、以下の点に注意が必要です。
1. 免責の範囲を具体的にする
通信障害、天災、第三者による不正行為など、免責の対象を明確に絞り込む。
2. 故意・重大な過失は免責しない
「当社の故意または重大な過失による場合はこの限りでない」など、サービス運営者側が責任を負う場合をできるだけ明確にする。
3. 専門家のレビューを受ける
法律や業界の特性に即したチェックを受け、内容の精度を高めることが重要です。
規約の見直しは定期的に
事業内容の変更や法改正、新たな判例が出ることで、適切な規約の内容は変わっていきます。
先述の消費者契約法も、平成28年、平成30年、令和4年と改正が行われ、無効や取消可能となる範囲が拡大しています。
そのため、最低でも年1回は規約を見直し、必要に応じて修正することを強くおすすめします。
まとめ
免責条項は事業者のリスク管理に不可欠な一方で、消費者契約法に反すれば無効となります。
モバゲー事件のように、適格消費者団体による差止請求が実際に起こる可能性があることも理解しておく必要があります。
安心・信頼されるサービス運営のために、免責条項の内容は慎重に設計し、定期的な見直しを怠らないことが大切です。