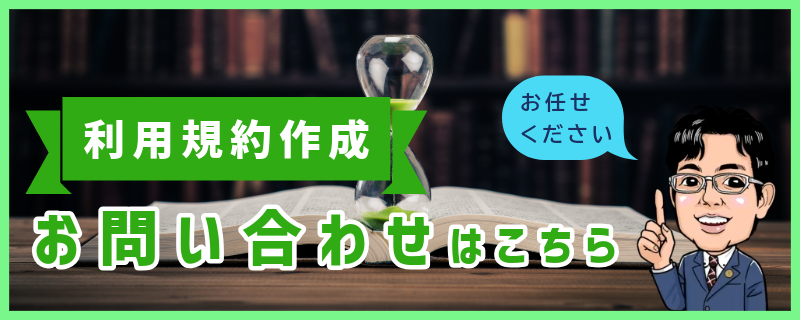SaaSなどのインターネットサービスやアプリ、ECサイトなどを運営する際に欠かせない「利用規約」。多くの事業者が導入している一方で、未だに「利用規約は契約書と違って好きなタイミングで自由に変更できる」という誤解が根強く残っています。
しかし、令和2年4月から施行された改正民法により定められた「定型約款」に関するルールが法的に整備され、その中で定型約款の変更に関するルールも定められました。
一般的に多くの利用規約がこの定型約款に該当すると考えられますので、この改正によって、サービス提供者が一方的に利用規約を変更するということに関して一定の制限が設けられています。
今回は、「利用規約の変更は自由ではない」という点について、令和2年改正民法の定型約款の考え方を交えて解説します。
利用規約も契約の一種
まず前提として理解しておきたいのは、「利用規約も契約の一種である」ということです。
利用規約は、サービス提供者と利用者との間で交わされる「契約条件」を定めたものにほかなりません。
画面上で「同意する」ボタンを押すだけで契約が成立するとはいえ、その効力は書面による契約書と変わるものではなく、法的な拘束力を持ちます。
つまり、サービス提供者が規約を一方的に変更するということは、「一方の当事者が勝手に契約内容を書き換える」ということに等しく、原則としては許されません。
令和2年民法改正で導入された「定型約款」のルール
定型約款とは、サービス提供者が多数の利用者との間で反復継続して締結する契約の内容を、あらかじめ定めておく文書を指します。まさに利用規約がその代表例です。
改正後の民法では、以下の2点が大きなポイントです:
① 定型約款の変更は「合理的理由」が必要
民法第548条の4では、定型約款の変更について以下のように定めています。
定型約款の変更が、
・その変更が「利用者の一般の利益に適合する」場合、
・または「契約の目的に反せず、かつ変更の必要性・内容の相当性等からみて合理的である」場合に限り、
提供者が一方的に変更できる。
つまり、サービス提供者が好きなタイミングで、好きな内容に規約を変更することはできません。「合理性」や「利用者にとって不利益にならないか」といった観点が求められるのです。
② 規約変更には「周知」が必要
さらに、定型約款の変更には「変更の効力が発生する時期」や「変更内容」などをあらかじめ利用者に周知する必要があります。変更の通知方法も、利用規約の中で明確に定めておくことが望ましいです。
「いつでも規約を変更できます」という条文のリスク
実際のところ、現在でも多くのウェブサービスの規約に、
「当社は、利用者の承諾を得ることなく、いつでも本規約を変更できるものとします」
といった条文が見受けられます。
これは(有効か無効かは不明確ではありますが)民法改正前には一般的だったルールでしたが、定型約款という概念が定義され、その変更のルールについても定められている現在の民法では、こうした一方的な変更条項は「無効」と判断される可能性があります。
特に、規約の変更が利用者に不利益を与える内容である場合、民法の趣旨に反するものとしてトラブルの原因となるおそれがあるといえます。
適法な変更条項の記載例
では、定型約款として適法な変更規定を記載するには、どのようにすればよいのでしょうか。以下に、改善された例を紹介します:
「当社は、法令の変更、サービス内容の変更、またはその他の合理的な理由に基づき、本規約を変更することがあります。この場合、当社は変更後の規約の効力発生時期および内容を、効力発生日の少なくとも〇日前までに当社ウェブサイト上に掲載するものとします。」
このように「変更理由の合理性」と「変更の周知手続き」を明記しておくことが、現在の法制度においては不可欠です。
消費者保護の観点から見た規約変更
定型約款のルールは、単に法的な制限というよりも「消費者保護」のための制度として位置づけられています。利用者が不利益を被るような一方的な変更がされないよう、一定の歯止めをかけているのです。
サービス提供者側としても、信頼性を高め、不要なトラブルを避けるためにも、民法に準拠した規約の整備は重要なリスクマネジメントとなります。
まとめ:いま一度、利用規約を見直そう
改正民法により「利用規約は自由に変更することができる」という時代は終わりました。
現代の法制度においては、サービス提供者にも一定のルールが求められており、それに応じた利用規約の見直しが必要です。
特に定型約款の規定が適用される以上、規約変更には「合理性」と「周知」の要件を満たすことが不可欠です。
もし、現行の利用規約に「随時変更可能」といった表現が残っている場合は、すぐにでも見直しを検討してみることをお勧めいたします。
利用者との信頼関係を築き、安心して利用してもらえるサービス運営のためにも、法改正への対応は重要なステップです。